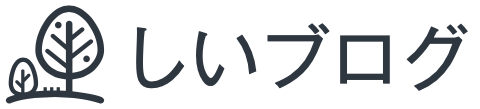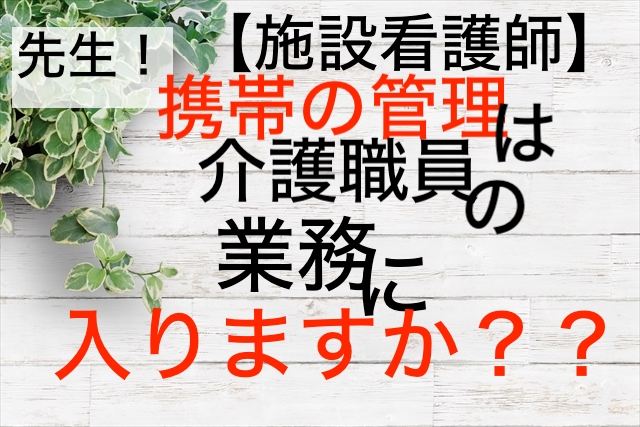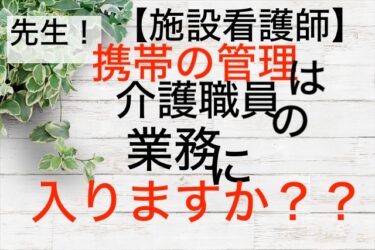こんばんは!しいです!
私事ですが仕事以外はイヤホンでyoutubeやポッドキャストを常に聞いています。
携帯依存症と言っても過言ではないくらい、スマホが手放せません。
自分がおばあちゃんになってもラジオだけはかけといて欲しいと思う今日この頃。
今回は、施設に入所される方が携帯を持ち込むことが増えてきている件をテーマにします。
・・・必要ですね。携帯コンシェルジュさん。常駐して欲しいです。
ある意味、ビジネスチャンスなんじゃないかと感じています。
もし、興味がある方は最後まで読んでいっていください!
携帯コンシェルジュが必要だ!
コンシェルジュという言葉の意味は? コンシェルジュとは、ホテルにて観光スポットの案内、チケットの準備、旅行のプランニングまで、お客さまの多くのリクエストに応えるプロのスタッフのことです。 最近ではホテル以外にも、病院、駅、レストラン、百貨店、高級マンションなどに活躍の場を広げています。(Googleより)
入居者様の携帯の操作や不具合の対応について快く見てくれるスタッフ、欲しいです。
笑顔で優しく、「これはですねぇ」と言いながらゆったりとした時間の流れで対応してくれる方。
介護施設にも活躍の場、ありますよ!
要介護3以上の方でも携帯が必要な理由
要介護3以上としたのは、特養の施設入居の基準です。ただ、要介護1でも2でも同じことが言えると考えています。
要介護度3以上の方の携帯電話を利用することは、以下の理由で必要な場合がありますが、同時に正しいサポートが必要なことも考慮しなければなりません。
②余暇・娯楽:携帯電話やスマートフォンを使って動画視聴やラジオを聴くことができます。携帯に詳しい人がいれば、高齢者が動画視聴方法のサポートを受けて、楽しむことができます。
携帯の所持が当たり前な時代、高齢者の方も元気な場合使いこなせている方がたくさんいらっしゃいます。もちろんご家族も携帯を持っていらっしゃいます。入所の時も流れで使えると思って持たせるのかなと考えています。
携帯の操作が簡単にできる施設職員は実は少ないという事実😅
法整備や制度が追いついていないのが一番悪いと思っています・・・
テレビのリモコンの操作をするように、ラジカセの周波数を合わせるように、そんな感覚で携帯が操作できる職員は実は少ないです。
特に携帯は高額で個人の大切な持ち物、さらにプライバシーの塊という印象です。他人のスマホは正直触りづらいです。
・他人の携帯を操作することに抵抗があります。見られては困る写真や電話帳やLINEなどあるのではないか?と不安に感じています。
・何かのきっかけで全部消去させてしまったらどうしようと考えています。
・誤って落として画面が割れたり、ガラケーだと折れてしまったら責任取れないと思っています。
・アンドロイドやiphoneなど使い慣れてないスマホの操作はできません。
・そもそもスマホや携帯の操作が苦手な職員がいます。
施設職員は携帯ショップの店員さんではないことをお知らせします
私は、息を吸うかのようにスマホを触っているので、操作を頼まれても「オッケー」とパパパッと対応できます。それでも、普段使い慣れていない機器の操作にはちょっと手間取ります。
苦手な職員にとってはちょっと厳しいかなぁと感じます。
入居者さんの携帯電話が同時多発的に鳴る件
ちょっと前に見た光景ですが、3人くらいの部屋から同時多発的に携帯の着信が鳴り出したユニットがありました。職員が大急ぎで取りに言っていました。ご家族の方が入所の方の声を聞こうと思ってかけているようでした。
職員は通常業務であるおむつ交換や入浴介助をこなしている状況で、つい出れない場合があります。要介護3以上の方は、携帯がなっても着信音が聞こえないことが多いです。さらに、スマホの操作をするという認識ができないことも多いです。代わりに職員が大急ぎで取りにこうとしても出れない場合があります。
取れなかった時はすぐに折り返して謝罪。最近の状態をお伝えしてご本人に取り次ぐといった流れです。
「先生!バナナはおやつに入りますか?」という質問の代わりに「先生!携帯の管理は介護職員の業務に入りますか?」と誰かに聞いてみたいです。
入所の方のサービスはどこまで必要か?考えてみた。
携帯電話の管理について、他の業務をこなしながらどこまで対応できるのか?考えてみました。
実際に対応している、もしくは想像してみて例を挙げてみます。
・携帯を充電しておく。・・・皆さんしているようですね。常に首からかけている方はちょっとてこづります(笑)
・着信が来たらご本人に電話が来たことを伝え通話ボタンを押して耳まで持っていく。・・・・着信に気づけばしていますね。毎日何時にかけて欲しいという希望もあるようで対応できる範囲でしているようです。
・通話が終わったら📞通話を切る。・・・会話が終わったか確認して対応していますね。
・入居者様が電話をかけたいと希望があった場合・・・どなたにかけたいのか?その方が電話帳にあるのか?お相手的に今かけてもいいのか?めちゃくちゃ考えてからしますね。事前にいつでもかけてOKが出ていればいいのですが、入居者様との関係性なども知らずにかけてしまう場合はかなり考えます。また、通話料が発生してしまわないか不安です。
・動画が見たいと希望があった場合・・・その携帯の料金プラン的に動画を見ていいプランなのか?考えてしまいます。えげつない使用料金の請求が来てしまわないか心配します。事前にご家族に許可が必要ですね。動画の好みがわかるまではどれがいいか?確認作業が付随してきますね。
・ネットで買い物を希望された場合・・・流石にこればまだ事例がありません。こればキッパリできないというかもしれませんね。
ご年齢的なものかラインなどのメッセージの送受信やネットでのショッピング・ゲームなどは今までありません。電話がメインかな。60代や70代の方は動画視聴もされている印象です。
お食事や入浴・おむつ交換やトイレ介助などに加えた業務?となりますが、業務というよりプラスアルファのサービスとなります。テレビやラジオみたいにちょっとしたことになってくれればいいのですが・・・
最後に:どなたか、携帯コンシェルジュという専門職を作ってください!
時代が進みましたね。携帯を持ち込む要介護者が増えてきているのは現状です。使いこなせない方が多く、操作が職員になることが多いです。
施設での決まりが曖昧な場合が多く、なしくづし的に管理は現場の職員がしています。
携帯は高価なものです。壊れたり失くした場合、職員の責任になることが予想されます。
今後も携帯の持ち込みが続くようであれば、専門職を作って欲しいのが現場からの希望。もしくはそもそも持ち込まない方がいいかなと感じます。
お互いに不安なく、携帯を支えていただけたらいいなと思いました!
皆さんはどんな意見をお持ちでしょうか?ぜひ、X(@shiiblog)のリプでコメントください。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。